Canvaの「一括作成」でイベント準備を劇的に効率化!保護者会向け活用術
- 自習ノート2
- 7月4日
- 読了時間: 8分
更新日:8月21日
はじめに
ビジネスイベント、セミナー、カンファレンス、懇親会など、参加者の名前を記した席札やネームカードが必要になる場面は少なくありません。
手作業で一枚一枚作成するのは時間も手間もかかりますが、Canvaの「一括作成」機能を活用すれば、デザイン性の高い席札やネームカードを短時間で効率的に作成できます。
この記事では、Canvaの「一括作成」機能に着目し、ビジネスイベントでの席札/ネームカード作成を例に、その活用方法を詳しく解説します。
イベント主催者や担当者の方がイベント準備をスムーズに進められるよう、具体的な手順や便利な機能、さらにデザインのポイントまで、分かりやすくご紹介します。
自社・他社の役職名や名前を差し替えて、すぐに使えるように汎用的な内容でお届けします。
目次
1. Canvaとは?ビジネスシーンでの活用

Canvaは、デザイン初心者からプロまで、幅広い層に利用されているオンラインのグラフィックデザインツールです。
豊富なテンプレートと直感的な操作性で、誰でも簡単にプロ並みのデザインを作成できます。プレゼンテーション資料、SNS投稿画像、チラシ、ポスターなど、様々な用途に対応できるため、ビジネスシーンでも広く活用されています。
ビジネスシーンでのCanva活用例:
マーケティング資料作成: プレゼンテーション資料、インフォグラフィック、SNS広告
広報・販促資料作成: チラシ、ポスター、パンフレット
社内資料作成: 報告書、議事録、社内報
ブランディング: ロゴ、名刺、Webサイトデザイン
Canvaは無料版でも十分な機能を備えていますが、Canva Proにアップグレードすることで、さらに多くのテンプレートや素材、便利な機能が利用できるようになります。
例えば、ブランドキット機能を利用すれば、ロゴやブランドカラーを登録しておき、一貫性のあるデザインを簡単に作成できます。
2. Canva「一括作成」機能とは?

Canvaの「一括作成」機能は、同じテンプレートをベースに、名前や役職、会社名などの異なるデータを効率的にデザインできる便利な機能です。
例えば、イベントの招待状や名刺、席札/ネームカードなど、同じフォーマットで複数のデザインを作成する場合に、非常に役立ちます。
「一括作成」機能を使用することで、手作業で一つずつデータを入力する手間を省き、大幅な時間短縮を実現できます。
また、データの入力ミスを防ぎ、デザインの統一性を保つことができるため、クオリティの高い成果物を作成できます。この機能は、Canva Pro、Canvaチーム、Canva教育版、Canva for NPOをデスクトップで使用するユーザーのみが利用できます。
一括作成機能のメリット:
時間短縮: 大量のデザインを効率的に作成
品質向上: データ入力ミスを防止し、デザインの統一性を維持
コスト削減: デザインにかかる人件費を削減
柔軟性: CSVやExcelファイルからデータをインポート可能
カスタマイズ性: 各要素のデザインを個別に調整可能
3. ビジネスイベントでの席札/ネームカード作成事例

ここでは、Canvaの「一括作成」機能を活用して、ビジネスイベントでの席札/ネームカードを作成した事例をご紹介します。ある企業では、業界向けのカンファレンスを開催することになりました。参加者は100名で、席札/ネームカードには以下の情報を記載する必要がありました。
氏名
役職
会社名
(オプション)肩書きや専門分野
(オプション)QRコード(名刺情報へのリンク)
これらの情報を手作業で入力するのは大変な作業ですが、「一括作成」機能を使えば、簡単に席札/ネームカードを作成できます。
席札/ネームカードに記載する情報:

[プレゼン用追記]この事例は、様々なビジネスイベントに置き換え可能です。
社内研修: 参加者の所属部署や役職を記載
顧客向けセミナー: 参加者の会社名や業界を記載
展示会: ブース担当者の名前と連絡先を記載
[社名・氏名変更例]
自社:〇〇株式会社、マーケティング部 部長 〇〇 太郎
他社:△△株式会社、代表取締役社長 □□ 花子
4. Canvaを使った席札/ネームカードデザインのステップ

Canvaで席札/ネームカードをデザインする手順は以下の通りです。
ステップ1:テンプレートを選択Canvaにログインし、「席札」または「ネームカード」を検索します。用途やイベントのテーマに合ったテンプレートを選択します。ビジネスイベント向けのシンプルなデザインや、会社のロゴを配置できるテンプレートを選ぶと良いでしょう。
ステップ2:必要な情報を配置席札/ネームカードに記載する情報を配置します。
氏名
役職
会社名
(オプション)肩書きや専門分野
(オプション)QRコード
ステップ3:一括作成左側のサイドパネルから、一番下の[一括作成]を選択。次に[データをアップロード]をクリックしてデータの追加画面を表示します。データは手動でも入力できますが、必要なデータを入力済みのExcelファイルかCSVファイルをアップロードする方が確実&簡単です。
ステップ4:ExcelファイルをアップロードExcelファイルには、席札/ネームカードに必要な情報を入力しておきます。CanvaにExcelファイルをアップロードする際は、あらかじめExcelを終了しておきましょう。
ステップ5:データの接続取り込んだデータを、デザインに反映させます。デザインの変えたい場所を右クリックして、右端の[…]をクリック。次に、[データの接続]を選び、該当の項目を選択します。必要な項目を連携したら、一括生成の[続行]をクリックしましょう。
ステップ6:生成確認画面が表示されるので、問題なければ「生成」ボタンをクリックします。すると、Excelファイルに登録されたデータに基づいて、席札/ネームカードが自動的に生成されます。
ステップ7:調整生成された席札/ネームカードを確認し、文字のサイズや位置、フォントなどを調整します。必要に応じて、イラストや写真を追加することもできます。企業のロゴやイベントのテーマカラーに合わせて、デザインを調整すると、統一感が出てよりプロフェッショナルな印象になります。
5. 出力用紙に合わせたサイズ調整
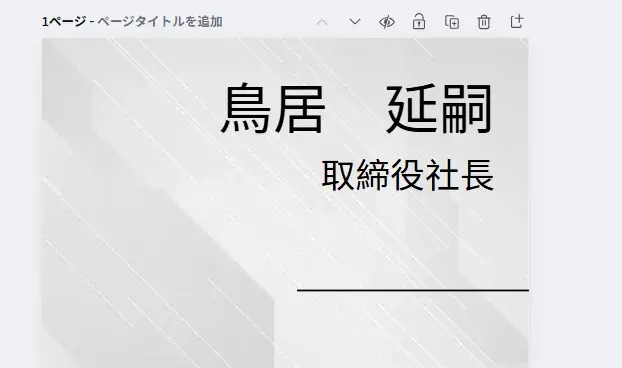
デザインが出来上がったら、次は出力です。ここで重要になるのは、出力する用紙のサイズ。作成した席札/ネームカードが規定のサイズで設定されているかを確認し、必要に応じて調整します。
Canva Proでサイズ変更する方法:
デザイン編集画面を開き、「ファイル」メニューから「サイズ変更」を選択
希望のサイズを入力(例:名刺サイズ、A4サイズ)
「コピーしてサイズ変更」をクリック
6. Canva素材の活用ポイント

Canvaは、豊富なイラストや写真、アイコンなどの素材を提供しています。これらの素材を活用することで、より魅力的な席札/ネームカードを作成できます。
素材を選ぶ際のポイント:
テーマに合わせる: イベントのテーマや企業のブランドイメージに合った素材を選ぶ
統一感を出す: 複数の素材を使用する場合は、テイストを統一する
著作権に注意する: 無料素材を使用する場合は、利用規約を確認する
[プレゼン用追記]
企業のロゴを配置する: 企業のロゴを配置することで、ブランドイメージを強化できます
イベントのテーマに合ったアイコンを使用する: イベントのテーマに合ったアイコンを使用することで、視覚的に訴求力を高めることができます
7. Canva一括作成機能、ココがすごい!
Canvaの一括作成機能は、他のデザインツールと比較して、以下の点で優れています。
使いやすさ: 直感的な操作性で、初心者でも簡単に使いこなせる
テンプレートの豊富さ: 多種多様なテンプレートが用意されており、デザインの幅が広がる
連携機能: ExcelやCSVファイルとの連携がスムーズに行える
カスタマイズ性: 各要素のデザインを細かく調整できる
コストパフォーマンス: 無料版でも十分な機能を備えており、有料版もリーズナブルな価格設定
8. まとめ
Canvaの「一括作成」機能は、イベント準備を効率化し、クオリティの高い席札/ネームカードを作成するための強力なツールです。この記事で紹介した手順やポイントを参考に、ぜひCanvaを活用して、ビジネスイベントを成功に導いてください。
Canvaを活用することで、以下のメリットが得られます。
イベント準備にかかる時間と労力を大幅に削減
プロ並みのデザインを手軽に作成
参加者に好印象を与える、洗練された席札/ネームカードを制作
次のアクション:
Canvaに登録して、無料テンプレートを試してみる
Canva Proにアップグレードして、さらに多くの機能を利用する
今回の記事を参考に、実際に席札/ネームカードを作成してみる
この記事が、皆様のイベント準備のお役に立てれば幸いです。
今回はこれで終わりです。次回もお楽しみに!
<自習ノートについて> 当社では教育機関向けの生成AI導入支援サービスも提供しています。
生成AIの導入からその効果的な活用方法、さらに継続的なパフォーマンス分析・改善までを一気通貫でサポートします。
最近開催した生成AI導入セミナーでも、多くの教育現場の方々からご好評いただきました。これからのAI活用にご興味のある方は、ぜひこちらのリンクよりお問合せください。
自習ノートのサービスについての詳細や、お問い合わせはこちらのリンクからどうぞ。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!





コメント